|
10月の夕暮れはもう十分に風が冷たくなっていました。営業時間の終了間際にドドンパでぶっ飛ばされて、ガラスの観覧車で怯えた余韻を残しながら、私たちは互いに上機嫌で駐車場に向かいました。
薄暗くなった場内は、帰りを急ぐ車のヘッドライトに照らし出されていました。その中で、白のシビックTYPE-Rが隣の車と頭を向かい合わせて何かごそごそやり始めていました。私はきっとバッテリ上がりのレスキューでもしているのだろうと思いながら自分の車に乗り込みました。しかし私がエンジンをかけて1分もしないうちに、TYPE-Rは片づけ始めて行ってしまいました。充電時間が短すぎるのではないか、そう思いながら運転席に座って少し様子を見ていました。取り残された車は相変わらずボンネットを開けたままでした。私は声をかけるべきか迷いましたが、明らかに途方に暮れている感じだったので、歩いていって話かけました。坊やのような青年と、ブロンドの女性がいました。ともに大学生くらいに見えました。
「バッテリでも上がったんですか。」
「はい、今ディーラーに勤めてるという人が見てくれて、バッテリを充電したけどセルがロックして回らないって言ってました。これからJAFに電話しようかと思っています。」
私は、おそらくそれはないだろうと考えました。なぜなら富士急の駐車場まで自走できて、駐車中にセルモータがロックする可能性は極めて低いと言えるからです。
「何かライトはつけっぱなしになっていませんでしたか。」
「スモールを消し忘れたみたいです。」
坊やのような青年が控えめに言いました。
「そうですか。それならもう一度私が試してみましょうか。それでダメならJAFに頼むなり考えれば良いと思いますよ。」
「はい、そうしてもらえれば助かります。」
私は自分の車のボンネットからスペアタイヤを取り外し、奥にあるバッテリと相手の車のバッテリとをブースターケーブルで接続しました。それからしばらく運転席で若干回転を上げながら、相手の車が充電されるのを待っていました。
「あっ、ついた!」
そう叫ぶのが運転席の私にまで確かに届きました。ルームランプがうっすらと灯り、やがてしっかりとした希望の明かりになりました。暗く寒い中で明かりが灯るのはうれしいものです。
「もう少し充電するので、待っていて下さい。」
私はルームランプを消すように伝え、充電し続けました。
それからしばらく充電した後に相手の車のエンジンをかけ、さらに充電を重ね、大丈夫と判断しました。そしてケーブルを外す作業をしているとブロンドの女性が声をかけてきました。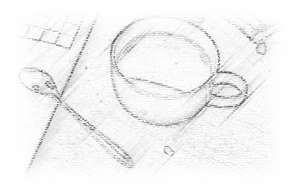
「あの、お礼にこれで帰りにコーヒーでも飲んで下さい。」
そう言って財布から2千円を出しました。
「いえ、お金はいりませんよ。」
「そんな、寒い中やってもらって本当に助かりました。受け取って下さい。」
「お金は、いらないですよ。」
そんなやりとりが続いて、とうとう彼女はケーブルを抱える私の腕に2千円をねじ込んできました。
「お金はいつでも欲しいですよ。でもこのお金は欲しくない。これは仕事じゃないから・・・」
私は彼女の車のフロントガラスとワイパの間に2千円を挟んで自分の車に戻り黙ってブースターケーブルを巻いていました。
「何て優しい人なんだろう。」
彼女はワイパーから取り外した2千円を胸のあたりで両手で握り締めてそう言いました。そんな台詞が出てくるのはドラマの世界だけかと思っていましたから、私は少し恥ずかしくなってしまいました。
「必ずバッテリ上がりを起こす人がいるから、今度はあなたが助ける番です。ブースターケーブルがあれば、誰でも助けられるから。」
私はそう言いながらトランクに巻いたケーブルをしまい込みました。
「そのお金でブースターケーブルを買って下さい。」
彼女は握っていた2千円を見ていました。
「どこで売ってるんですか?」
「ホームセンターでもカー用品店でもありますよ。もしあなたが助かったと思ったなら、何かお返しがしたいと思ったのなら、それを困っているだろう未来の人に向けて下さい。」
彼女の善意は彼女に託し、私たちは駐車場を後にしました。
人はひとりでは生きていけない。だからこそ、他の人に対する優しさが必要だと思う。優しさの連鎖。それさえあれば、みんな幸せになっていけると思うのです。
私も未熟な時に色々な方に助けてもらったのですから。
|